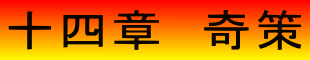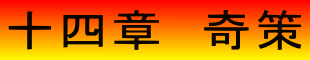
ドン――ドン――ドン――
織田、羽柴両軍からほぼ同時に陣太鼓が鳴り響き、前線で戦っていた将兵達が後退していく。
「いや〜、遠路ようお出で下さった。これでこの戦はもう勝ったも同じじゃわ、
この秀吉、感激の極みに御座る」
そういって秀吉は来訪者の手を取りニンマリと笑う。
「なに、筑前守殿の軍略があれば我らなどおらずとも、信長公亡き織田家如き、物の数では御座るまい」
中国の太守、毛利 少輔太郎 輝元が答える。
織田・徳川連合軍と羽柴軍が一進一退の攻防を繰り広げていたところに、遂に秀吉の切り札とも
言うべき増援、毛利軍が当主の輝元自ら叔父の小早川 又四郎 隆景とともに、
一万を超える兵を率いて着陣した。
それを見た信正と家康は一旦兵を退き、秀吉も下手に追わず、一時休戦状態となった。
両軍ともその大部分を未だ投入しておらず、小手調べといった形になったわけだが、
そんな中で主だった者では、井伊直政の側近である木俣守勝が討死、細川忠興が鉄砲で肩を
打ち抜かれ重傷を負い、羽柴方でも軍目付けとして高山重友隊にいた、七本槍の一人である
片桐 助作 且元が佐久間盛政に討たれ、中村一氏も刀傷を負って参戦不可能となった。
「おのれ盛政め…まさか助作が敗れようとは・・この仇、必ず討ってくれる!!」
且元と同じく七本槍にその名を連ねる加藤 虎之助 清正は血のにじむほど拳を握り締め、
自分の目の前で討たれた同輩の敵討ちを固く心に誓った。
その日はそのまま対陣したまま陽が落ち、両軍は次の朝を待つことになった。
織田本陣には、柴田勝家、丹羽長秀、滝川一益、池田恒興の宿老らにその旗下の将が集まっていた。
「明日こそ、敵陣に切り込み、あの猿の首を落としてくれるわ!」
前哨戦では出番のなかった勝家は、火を吐くように戦意を滾らせる。
「明日は某も、父上や兄上に負けぬよう戦いたく存じまする」
「うむ、よう言うた勝政!その方の義父は鬼も逃げ出す剛勇よ。盛政に負けぬよう、励め」
勝家の甥で養子になった、勝政の意気込みに信正も小気味良さを感じる。
「盛政も、今日の活躍、見事であったぞ」
「ははっ、有難き御言葉!明日も今日以上の槍働きを御見せ致すでありましょう」
信正は無類の猛者好きで、それへの賞賛を惜しまない。盛政もそれに感激の言葉を返す。
「うむ、権六の家中は豪傑揃いで大いに結構、羨ましい限りじゃ。だが、猿の得手とするは
謀りの戦。正面切っての戦では我らに利ありとならば尚の事何か仕掛けてくるに相違なし。
無闇と攻めかかるは下策ぞ」
織田家中で<進むも滝川、退くも滝川>と評された一益が言う。一益自身も正規の白兵戦よりは、
調略戦や不正規戦などを得意とし、それ以上に鉄砲術に秀で、織田家に銃火器の差配において
一益の右に出るものはいないとされる。
「なんの、筑前如きの猿知恵など恐れるに足らん!」
血気盛んな盛政が声を荒げて豪語するが、それを長秀が嗜める。
「待て待て、その猿知恵に今までどれ程の者達が手玉に取られてきたか、玄蕃とて承知しておろう」
「そ、それは確かにそうで御座りまするが・・されど丹羽殿、攻むること無しに戦には勝てませぬぞ」
「判っておる。それ故我らが信正様のもとに集まっておるのではないか」
長秀がにこやかに言い、そこで信正が口を開いた。
「左様。毛利が援軍として現れた以上、父上御愛用の数で圧倒する戦はもはや出来ぬ。
ならば如何に策を敷くかこそ肝要。五郎左、左近、その方らの着眼もっともである」
有難き御言葉、と両者平伏する。
「して、その策であるが・・・その方ら島津を知っておるか」
信正の突然の問い掛けに一同はきょとんとして互いの顔を見合わせる。
「島津とは、薩摩の守護大名の、あの島津で御座りまするか」
恒興が口にすると信正は機嫌よくデ、アルと答える。
「島津輩は田舎侍ではあるが、であるが故に中々に面白い策を弄しおるわ」
「なれば此度はその島津の策を用いられまするか」
「うむ、西国では『島津の釣野伏』と呼ばれておる。さぁ、各々近う寄れ」
そう言って信正は秀吉を葬るための奇策を重臣達に説明するのであった。