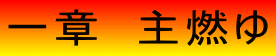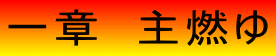――――人間五十年 下天の内を暮らぶれば 夢幻の如く也
一度生を受け 滅せぬ者の在る可きか…――――
主君は紅蓮に燃え盛る火炎の中で舞い続ける。
それを見ていた男は助けに向かおうとするのだが、なぜか体がまったく動かず、声ひとつ出せない。
上様、上様、と心の中で叫んでいると主君は不意に苦笑を浮かべ語りだした。
「口惜しや、キンカ頭めにしてやられたわ…。この上は是非もなし。
我が天下、汝(われ)に託す。キンカ頭では世は治められまい。
猿が我が後を狙うであろうが汝に抗うようならば、構わぬ故蹴散らしてやるがよい」
男は、主君言葉の意味がまるで判らない、といった様子だった。
これではまるで主君は死ぬようではないか、と男は思った。
しかしその考えを裏付けるように、虚空を見つめ主君は続ける。
「人間五十年……あと一年及ばなんだわ。権六!さらばじゃ!!」
そして主君は男に背を向け、炎の中へと消えていった。
それと同時に男の体に自由が戻った。男は考えるよりも先に走り出し、叫んでいた。
「上様、お待ち下され!!!!!!!」
男は主君のあとを追おうとしたが、それを拒むかの如く目の前の炎の壁が崩れ、男の上に覆い被さった。
男は、汗まみれになり肩で息をしながら目覚めた。
あまりにハッキリとした夢だったために、それが夢だと理解するのに
かなり戸惑った様子ではあったが、少し落ち着いたようで夜風にあたろうと
寝所を出た。外では煌々と篝火が焚かれており思いのほか明るかった。
不寝番の小姓は不覚にも居眠りしており、男が寝所を出たことにも気付いていない。
常なら、怒鳴りつけて喝の一つでも入れてやるところだが、今は何やら胸騒ぎがし、
それどころではなかったので放っておいた。
外に出た男は、遠く離れ見えるはずのない京の方を眺めていた。
すると、ふと都が燃ゆるのが見えた気がしたが、次の瞬間には見えなくなっていた。
六月二日の夜明けが近いらしく、既に東の空が白み始めている。
昇り始めた日の光が男の顔を照らし、その容貌を露わにする。
数多の修羅場で刻まれてきたであろう数々の傷が、ただでさえ凄味のある
男の顔をさらに際立ったものにしている。
この男こそ、織田家家老筆頭、譜代中の譜代で戦場での剛勇振りから
鬼と呼ばれた、柴田権六勝家であった。